学術大会で用意すべき参加費決済方法とは?259大会のデータを集計して見えたこと
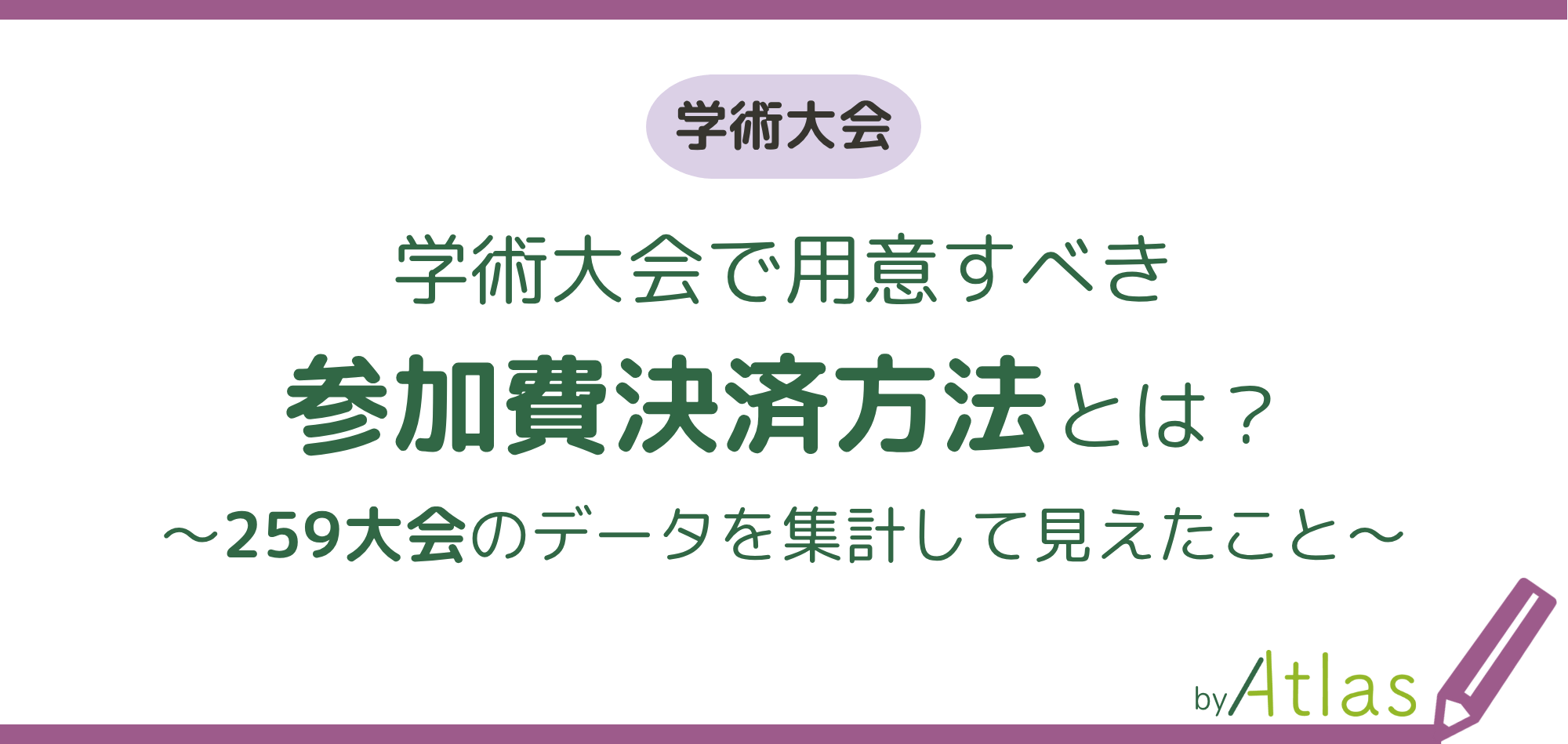
こんにちは。学術大会グループの髙橋です。
秋は学術大会のシーズンですね。アトラスでは年間300以上の学術大会を支援しておりますが、その約半分が9~11月の3カ月間で開催されるんです。ご存知でしたか?
さて、今回ご紹介するのは、学術大会の準備を進めるうえで避けては通れない参加費の決済方法についてです。
「どの決済方法を選ぶのが参加者にとっても、事務局にとっても正解なんだろう?」
「他の学会は一体どうしているのかな?」
「複雑な手続きや入金チェックで事務作業が煩雑になるのは避けたい…」
このようなお悩みをお持ちの方に対して、実際に弊社の学術大会支援サービス「Confit」を利用した259大会(※)のデータを集計し、他学会の傾向とおすすめの参加費決済方法をお伝えします!
※直近1年間にConfitを利用した大会のうち、「参加登録機能」を利用した大会の数
初めて大会の事務局業務を担うことになった実行委員の方から、長年大会運営には関わっているものの「本当に今のやり方で大丈夫?」と最新のトレンドが気になっている学会事務局様まで幅広い方のお役に立てる記事となっておりますので、ぜひ最後までお付き合いください!
学術大会の参加費決済方法、主要な4つのパターンとは?【259大会のデータ集計】今、一番選ばれているのはどの決済方法?集計結果からわかることクレジット決済が「デファクトスタンダード」に銀行振込は国内大会と国際会議で大きな差コンビニ決済と当日支払いは極わずかおすすめの決済方法とその理由国内大会ならクレジット決済と銀行振込の併用がおすすめ国際会議では「クレジット決済のみ」で対応可能その他の決済方法についてコンビニ決済は導入ハードルがネック当日支払いは管理コストと混雑リスクが高い参加費管理を円滑にするためのポイント一度支払った参加費は「原則返金しない」ポリシーでの運用を従来の決済方法を廃止するときは緊急手段の準備も検討するまとめ
学術大会の参加費決済方法、主要な4つのパターンとは?
まずは、学術大会の参加費決済において採用されている代表的な4つのパターンとその概要を見ていきましょう。
| 決済方法 | 概要 | 特徴 |
| 銀行振込 | 参加者が指定の銀行口座に直接振り込む方法。所属機関による請求書払いを希望する参加者に必須となることが多い。 | ・導入が簡単 ・入金確認/消込作業が発生する |
| クレジット決済 | オンライン上でクレジットカード情報を使って決済する方法。近年、最も利便性が高いとして普及している。 | ・決済代行会社との契約や連携が必要 ・入金確認が自動化される |
| コンビニ決済 | 参加者が指定のコンビニエンスストアで代金を支払う方法。クレジットカードを持たない層の利用が多い。 | ・決済代行会社との契約や連携が必要 ・厳格な利用審査がある ・入金確認が自動化される |
| 当日支払い | 大会当日の受付で現金を支払う方法。 | ・事前に支払えなかった人への最後の受け皿となる ・受付混雑のリスクがある ・現金を管理するコストがかかる |
以上が学術大会で見られる主な決済方法です。
どの決済方法も一長一短であるため、それぞれの特徴を理解した上で、自学会の参加者層や運営体制に合わせて選択することが重要です。
なお、いわゆる「スマホ決済」「QR決済」と呼ばれるPayPayや楽天ペイ等は、学術大会においてはまだ普及していません。
【259大会のデータ集計】今、一番選ばれているのはどの決済方法?
それでは、ここからは実際に「他の学会がどうしているのか?」をご紹介していきます。
今回は私たちが支援してきた学術大会のデータを集計しました。
以下の表は、2024年9月~2025年8月の1年間にConfitを利用して参加費決済を実施した259大会における決済手段の導入状況を具体的に示したものです。
なお、このデータはあくまで大会としてどのような決済方法を用意していたかを表したものなので、実際に参加者が選択した決済方法とは関係ありません。
| 決済方法 | 導入大会数(259大会中)※ | 導入率 |
|---|---|---|
| クレジット決済 | 254大会 | 98.1% |
| 銀行振込 | 132大会 | 51.0% |
| コンビニ決済 | 13大会 | 5.0% |
| 当日支払い | 15大会 | 5.8% |
※導入大会数の合計が259と一致しない理由は、複数の決済方法を併用している大会があるため。
また、上記の結果を国内大会と国際会議にカテゴリ分けすると以下の結果が得られました。
国内大会
| 決済方法 | 導入大会数 (194大会中) | 導入割合 |
|---|---|---|
| クレジット決済 | 193 | 99.5% |
| 銀行振込 | 117 | 60.3% |
| コンビニ決済 | 13 | 6.7% |
| 当日支払い | 7 | 3.6% |
国際会議
| 決済方法 | 導入大会数 (65大会中) | 導入割合 |
|---|---|---|
| クレジット決済 | 61 | 93.8% |
| 銀行振込 | 15 | 23% |
| コンビニ決済 | 0 | 0% |
| 当日支払い | 8 | 12.3% |
集計結果からわかること
クレジット決済が「デファクトスタンダード」に
この集計結果から、もはやクレジット決済が学術大会の参加費決済における「デファクトスタンダード(事実上の標準)」となっていることが明確にわかります。
導入率は98%以上と、ほとんどの大会で採用されているのです。
クレジット決済が選ばれる理由
- 参加者の利便性の高さ:
- 参加者は時間や場所を選ばず、24時間いつでもどこからでも決済を完了できます。
- 支払い手続きが簡単かつ迅速であるため、参加者にストレスを感じさせにくく、参加意欲を維持できます。
- 事務局側の管理のしやすさ:
- 決済システムを導入することで、入金状況の確認や参加者データとの照合がほぼ自動化されます。
- 銀行振込のように入金確認をする必要がなくなり、事務作業の大幅な削減が実現します。
- 国際会議への対応:
- 海外からの参加者にとって、日本の銀行への海外送金は手数料が高く、手続きも煩雑です。クレジット決済であれば、国境を問わずスムーズに支払いが可能です。
銀行振込は国内大会と国際会議で大きな差
銀行振込は国内大会では導入率60%を超えている一方、国際会議では23%に留まります。
これは、海外送金は手間と手数料が大きいため、海外からの参加者が多い国際会議では敬遠されることが多いことを示しています。
コンビニ決済と当日支払いは極わずか
コンビニ決済と当日支払いはそれぞれ全体の5%程度で、導入率はかなり低いことが分かります。
詳細については後述しますが、大会運営の成功と効率化を目指すうえで、手間およびリスクが高いことが原因と考えられます。
おすすめの決済方法とその理由
259大会のデータと、これまで多くの学会運営を支援してきた実績に基づき、おすすめの決済方法とその理由を詳しく解説します。
国内大会ならクレジット決済と銀行振込の併用がおすすめ
集計データが示す通り、クレジット決済は参加者の利便性、事務局の導入・管理のしやすさの両面から、必須の決済手段であると言えます。
決済手数料として決済金額の3%程度が発生することが多いですが、得られる「事務作業の効率化」と「参加者の利便性向上」というメリットを考えれば必要なコストと見ていいでしょう。
ただし、クレジット決済では所属機関の規定で請求書払いを希望する場合や、クレジットカードを持たない参加者などをカバーできません。そのため、銀行振込も併用するのが理想的です。
銀行振込は「バーチャル口座」の活用がおすすめ!
クレジット決済と銀行振込を併用することで、より多くの参加者のニーズに応えることができますが、指定の口座に振り込んでもらう通常の銀行振込では入金確認の手間が発生し、事務局業務の大きな負担となります。
そこで、銀行振込を導入する際は「バーチャル口座」を活用することがおすすめです。
バーチャル口座とは、文字通りバーチャル(仮想)な口座番号を顧客(学術大会では参加者)や注文ごとに割り当てることで、自動的に入金確認や消込作業ができるサービスのことです。
アトラスが提供する「Confit」でもこの仕組みを利用することができ、決済手数料もクレジット決済より安価(Confitの場合は0.5%)に抑えられます。
国際会議では「クレジット決済のみ」で対応可能
海外からの参加者が銀行振込をしようとすると海外送金が必要になるため、手数料が割高であったり、事務局側で必要な手続きも煩雑になります。
そのため、海外からの参加者が多い国際会議では、手続きがスムーズで手数料も比較的抑えられるクレジット決済に一本化することも、合理的な選択肢となります。
その他の決済方法について
コンビニ決済は導入ハードルがネック
参加者の利便性を考えてコンビニ決済を検討する学会も多くありますが、集計結果の通り、実際に導入している大会は5%と極めて少数です。
主な理由としては、厳格かつ時間がかかる利用審査にあります。コンビニ決済の導入には、コンビニ本部による厳格な審査があり、審査期間も3カ月以上かかることがあります。急な大会準備には不向きで、導入ハードルが非常に高いのが実情です。
また、クレジット決済と銀行振込(バーチャル口座)でほとんどのニーズはカバーできるため、そこまでして導入するメリットは薄いというのが実際のところです。
当日支払いは管理コストと混雑リスクが高い
「どうしても事前に支払えなかった人のため」と当日受付での現金支払いを認めている大会もありますが、以下の2点の理由からあまりおすすめできません。
- 受付の混雑:当日、受付で現金の授受を行うと、単純に時間がかかり、受付の行列や混雑の原因になります。
- 現金の管理負担:現金の過不足が発生するリスク、徴収した現金の管理・精算、そして釣銭や領収書の用意など、想像以上の労力がかかります。
今まで当日支払いを受け付けてきた大会で廃止を決めるのは簡単なことではないかもしれませんが、今回ご紹介したデータの「当日支払いを認めている大会の少なさ」を根拠として変革を進めてみるのはいかがでしょうか。
参加費管理を円滑にするためのポイント
決済方法を決めればそれで終わりではなく、参加費管理を円滑にするためには運用ルールも大切です。
一度支払った参加費は「原則返金しない」ポリシーでの運用を
参加費の返金対応は、事務局にとって大きな負担となります。返金手続き、銀行手数料の計算、入金データの修正など、多くの手間とコストが発生するからです。
返金に関するトラブルを避けるためにも、大会規約や特商法に基づく表記に「一度納入された参加費は、理由の如何を問わず返金しない」旨を明確に記載することを強く推奨します。
もちろん、やむを得ない事情で柔軟に対応している事例もありますが、対応し始めるとキリが無くなってしまうため、一切返金には応じないというポリシーで運用している事例も存在します。
学会の規模や過去の慣例を考慮し、明確なルールを定めて周知することが重要です。
従来の決済方法を廃止するときは緊急手段の準備も検討する
採用する決済方法を変更する際、とりわけこれまで使えていた決済方法を廃止するような場合は、事前に告知をしていても参加者に多少の混乱が予想されます。
全参加者に理解していただき、スムーズに新しい決済方法に移行してもらうのが一番ですが、どうしても難しい場合は緊急手段として従来の決済方法を残しておくというのも一つの手です。
ポイントは、あくまで緊急手段のため、個別に希望があった場合のみ対応するということです。
決済方法を変えたことで参加者が減ってしまっては元も子もないので、なるべく穏便に移行したいという場合はこのような方法を検討しましょう。
まとめ
- 国内大会なら「クレジット決済&銀行振込」
- 国際会議なら「クレジット決済」
これが多くの学術大会に関わってきたアトラスとしての「おすすめ」の決済方法です。
結論としてはそれほど目新しいものではないかもしれませんが、実際のデータと紐づいていることで腑に落ちる部分もあったのではないかと思います。
また、今回ご紹介したのはあくまで「おすすめ」であり、どの学会にも当てはまる「絶対的な正解」があるわけではありません。
学会ごとに規模や予算も違えば、参加者層も文化も異なりますから、「参加者の利便性」「事務局の業務負担」「費用」等を鑑みて総合的に判断していただければと思います。
もっと詳しく「自分の学会には何が合っているのか知りたい」という方は無料相談フォームもございます!お気軽にお申し込みください。
当コラムについて
「IT×学術」で研究者を支援する株式会社アトラスが運営する当コラムでは、学会運営に関するお役立ち情報を発信中!
「学術大会」「会員管理」「ジャーナル」という重要度の高い3つのカテゴリを軸に、学会運営に関わるすべての方の疑問やお悩みを解消することを目指しています!
詳細はこちら




